
板橋区相続相談センター
運営元:イクシス法務会計総合事務所
〒171-0021 東京都豊島区西池袋1丁目2番1号アウルスクエア4F
営業時間:平日9:00~17:00
生前贈与
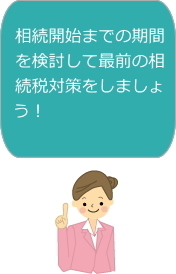
生前贈与とは被相続人が死亡する前に相続人等に財産を渡すことで、相続税対策の一つとして行われることが多いです。
また、相続税対策としてだけでなく、生前に意思を表明できる方法として有効な手法と言えます。
相続税対策における生前贈与については、いつ相続が生じるかで短期間で対策を施さなければならない方と長期間でいい方と方法が違ってきます。
長期間(10年くらい)で対策できる方は、生前贈与を繰り返し、着実に相続財産を相続人となる方に移転させていきます。
短期間で対策しなければならない方は、即効性があり、より効果的な方法を検討していかなければなりません。
続開始前3年以内の生前贈与は、相続財産に加算し、相続税の課税対象財産となるため、対策を実施する時期は、早ければ早いほど良い相続税対策になるということになります。
また、地主の方や資産家の方は、生前贈与で相続税対策をしても相続税がゼロになることは難しいと考えられますので、いかに「相続財産を増やさないか」、「納税資金として準備できるか」ということに重点をおくべきであると考えられます。
暦年贈与による生前贈与
暦年課税贈与による生前贈与とは、1歴年単位(1月1日から12月31日まで)の贈与を利用して生前に財産を相続人に移転させる方法です。
1年間で、基礎控除110万円までの贈与なら、受贈者(贈与を受ける方)に贈与税は生じません。
この基礎控除の範囲内で毎年地道に生前贈与をしていき相続財産となるものを減らしていくというケースも多くあります(連年贈与の認定には注意が必要です)。
ただし、「生前贈与加算」といって、相続開始前3年以内(相続の開始が平成29年4月20日の場合は平成26年4月20日以降)の贈与に関して、その贈与者の相続により財産を取得した方は、その相続の被相続人から、生前贈与により取得した財産の価額を相続税の計算に足し戻すことになります。
相続時精算課税贈与による生前贈与
相続時精算課税とは、平成15年に新設された贈与の形態で、高齢者の保有する財産を次世代に円滑に移転させ、それによる若年層の消費増を目的として創設されました。
相続時精算課税を適用するには一定の要件がありますが、特別控除額が大きく、また、相続税の計算に足し戻す贈与財産の価額は、贈与時の時価であることなど、利用の仕方によってはメリットもあります。一方、デメリットもありますので、慎重な判断を必要とします。
(1) 相続時精算課税を適用するための要件
1.受遺者(贈与を受ける人) 次の全てに当てはまる必要があります。
③ 贈与者の孫であること。
④ 贈与を受けた年の1月1日現在において20歳以上であること。
※推定相続人である直系卑属というのは、例えば親からみて、親が死亡した場合に財産を相続することになる子がこれに該当します。(子が死亡している場合には、代襲相続人となる孫などが該当します。)
2.贈与者 贈与をする年の1月1日において60歳以上である者
以上の要件すべてに該当すれば相続時精算課税による贈与をすることができます。
とくに注意したいのは受遺者と贈与者の年齢です。
1月1日にさかのぼって年齢を判定しますので、その年で20歳になる、あるいは60歳になる方は、適用可能年が翌年になります。
また、実際に相続時精算課税を適用する場合には、「相続時精算課税選択届出書」をその贈与に係る期限内申告書に添付して提出しなければなりません(戸籍謄本など、推定相続人であることを証明する書類その他一定の書類も併せて必要です)。
相続時精算課税選択届出書は一度提出すると、その贈与者についての相続が発生するまで撤回できないという決まりがありますので、注意が必要です。
また、たとえば、父親からの贈与については相続時精算課税を、母親からの贈与については暦年課税贈与を、というように、分けて選択することができます。
(2) 相続時精算課税による贈与税の計算方法
- 相続時精算課税による贈与税の特別控除額は2,500万円です。
よって、両親ともに相続時精算課税を選択した場合は、合計5,000万円まで贈与時点では無税で財産移転が可能です。 - 1年ごとに2,500万円の特別控除があるのではなく、相続時精算課税を適用し始めてから、その贈与者の相続が開始するまでの贈与通算で2,500万円です。
なお、通算で2,500万円を超える贈与があった場合は、その超えた部分について、金額の多寡にかかわらず、一律20%の贈与税が課されます。 - 暦年課税の贈与と異なり、足し戻しの対象となる贈与に年限はありません。すなわち相続時精算課税を適用した以後の年分の贈与についてはすべて、相続税の計算に足し戻します。足し戻す価額は、贈与時の時価です。
- 足し戻された贈与財産につき納付した贈与税額があるときは、その贈与税額を算出された相続税額から控除して、残りを納付します。
また、控除しようとする贈与税額がその相続税額から控除しきれない場合は、その控除しきれなかった贈与税額が還付される点が、暦年課税贈与と大きく異なる点です。
贈与税の配偶者控除
被相続人予定者の財産を生前に移転させるという観点から、贈与税の配偶者控除を利用した生前贈与も考えられます。
この制度は、婚姻期間が20年以上である配偶者間において、居住用不動産またはその取得のための金銭の贈与があった場合には、その贈与税の課税価格から2,000万円を控除する、といったものです。
結果、暦年課税の基礎控除額110万円と合わせて2,110万円まで贈与税がかかりません。
住宅取得促進税制の活用
最大1,200万円までの住宅取得等資金贈与にかかる贈与税が非課税となります。
暦年贈与(その年の1月1日から12月31日までの間に贈与を受けた財産額の合計)の基礎控除額110万を考慮すると合計1,310万円まで贈与税が非課税となります。
対象者は、父母および祖父母(直系尊属)からの贈与で、対象は贈与する年の1月1日に20歳以上の子・孫に限ります。適用要件は、平成33年12月31日までに契約した住宅取得に適用されます。
対象の住宅は非常に範囲が細かいことから、専門家にご相談することをおすすめします。
教育資金贈与の非課税制度
平成25年度税制改正において、「教育資金贈与の非課税制度」が創設されました。
平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に行われる教育資金に充てるための贈与について、一定の要件を満たした場合には、1,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。
贈与を受けた子や孫が30歳までに教育資金に使われなかった余ったお金については贈与税が課税されます。
【制度の概要】
受贈者の要件 : 30歳未満であること
贈与者の要件 : 受贈者の直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)
非課税の範囲 : 授業料等、教育機関に直接支払われるもの 1,500万円まで
習い事等、間接教育費 500万円まで
なお、使途が混同する場合であっても、上限は1,500万円となります。
申告の方法 : 適用を受ける旨等を記載した「教育資金非課税申告書」を信託金融機関を通じて納税地の所轄税務署長に提出
未使用分の精算 : 受贈者が30歳となるまでに使用しなかった信託の残金については、受贈者が30歳となった日において贈与があったものとされる
なお、受贈者が30歳となる前に死亡した場合には、残金につき贈与税は課されません
期中の運用としては、引き出しの際に使途を証明する書類を各金融機関に提出することとされています。
なお、教育資金の具体的範囲については、文部科学大臣が定める以下の金銭・ 学校等(大学・高校等)に支払われる入学金その他の金銭・ 学校等以外(塾・予備校等)の者に支払われる金銭のうち一定のもの
お問合せ・ご相談はこちら

| 受付時間 | 平日9:00~17:00 |
|---|
ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
遺言・相続の手続き(相続登記、相続放棄、遺産分割、相続税申告、相続税対策等)、成年後見制度(法定後見、任意後見)、遺言書作成のご相談なら、実績のあるイクシス法務会計総合事務所が運営する『遺産相続・成年後見相談センター』にお任せください。当事務所の司法書士・税理士が親身になって対応致します。
下記のような疑問をお持ちでしたら、どうぞお気軽にご連絡ください。
・急に家族が亡くなってしまいました。この後の手続きは、いったいどうすればいいの?
・祖父が亡くなった際、土地の名義変更してなかったけど、このままで大丈夫?
・今流行のエンディングノートってどんなもので、どうやって書くんですか?
・母が認知症になってしまい、成年後見制度を利用する必要があります。
・結局、費用はいくらぐらいかかりますか?
親切、丁寧な対応を心がけております。お気軽にお問合せ下さい。
| 対応エリア | 東京都(板橋区・練馬区・豊島区・北区)、和光市、朝霞市、志木市、富士見市、ふじみ野市、川越市、その他首都圏全域 |
|---|
サポートメニュー
イクシス法務会計総合事務所
(司法書士依田法務事務所・
石丸寛税理士事務所)
遺産相続・成年後見相談センター
主な業務地域
東京都(板橋区・練馬区・豊島区池袋等)、和光市、朝霞市、志木市、富士見市、ふじみ野市、川越市、その他首都圏全域
